こんにちは!ベーです。
今回は計算問題の総集編になります。

今まで4つの計算をやってきたからそのまとめだね。

今回は計算の順序に関するルールも扱っていくよ。
今まで習ってきた計算と併せて、順序の計算と「分配法則」も扱っていきます。
・四則の混じった計算をマスターしたい人
・計算の順序を確認したい人
・分配法則を理解したい人
はぜひチェックしてください!
四則の混じった計算

そもそも四則ってなんだっけ?
四則
四則とは4つの計算の総称を言います。
四則・・加法、減法、乗法、除法の4つをまとめたもの
今回の計算は4つの計算に加えて()や累乗が入った計算も解いていきます。
こんな例題を扱っていきます。
例 次の計算をしなさい
(1) \(3+(-2)\times4+(-6)\div(-2)\)
(2) \(-3\times(-5+3)\)
(3) \(20\div(1-3)^2-(-5)\)
自力でできる人はぜひ解いてみてください。
合っていた人は練習問題を解いてみましょう。
計算の順序
例の問題を活用しながら計算の順序について確認していきます。
乗法と除法
まずは、乗法と除法についてです。
例 次の計算をしなさい
(1) \(3+(-2)\times4+(-6)\div(-2)\)

乗法や除法は加法や減法より先に計算するよ!
計算のルール①
乗法(\(\times\))や除法(\(\div\))は加法(\(+\))や減法(\(-\))より先に計算する。
なので、今回の例の解答は次のようになります。
解答
(1)
\(\begin{align}
3+(-2)\times4+(-6)\div(-2) &= 3+(-8)+3 ・・①\\
&= -2
\end{align}\)
①左からではなく、乗法・除法から計算

\(\times\)や\(\div\)が出てきたら注意だね!
かっこ「( )」のある式
次はかっこのある式です。
\(\times\)や\(\div\)があってもかっこ「( )」があったら注意が必要です。
例 次の計算をしなさい
(2) \(-3\times(-5+3)\)

「( )」がある式の場合は、乗法や除法よりも先に計算するよ!
計算のルール②
かっこ「( )」のある式はかっこの中を先に計算する。
今回の例はこのようになります。
解答
(2)
\(\begin{align}
-3\times(-5+3) &= -3\times(-2) ・・①\\
&= 6
\end{align}\)
①\(\times\)からでなく()の中から計算

覚えることが多くなってきたな、、
ちなみに、かっこには「( )」、「{ }」、「[ ]」の3種類があります。
練習問題で扱いますが、計算の順序は「( )」、「{ }」、「[ ]」の順です。
どんな式であれ、「かっこから」を忘れずにいきましょう。
累乗
最後は累乗のある式です。
例 次の計算をしなさい
(1) \(20\div(1-3)^2-(-5)\)

累乗がある式は累乗から計算するよ!
計算のルール③
累乗がある式は累乗から計算する。
今回の場合は累乗がついている中身が加法になっているので、そこから計算します。
解答
(3)
\(\begin{align}
20\div(1-3)^2-(-5) &= 20\div(-2)^2-(-5) ・・①\\
&= 20\div4-(-5) ・・②\\
&= 5-(-5) \\
&= 10
\end{align}\)
①累乗のついている「( )」の中身から計算
②累乗の計算

先にする計算が多くてややこしいね(笑)
計算の順序まとめ
それぞれ確認しましたが、計算の流れは
累乗 ➡︎ かっこ ➡︎ 乗除
の順で確認して問題を解いてみてください!
分配法則

分配法則って( )の中身を掛けていくやつだよね
分配法則は小学校で習っていると思いますが復習です。
分配法則
次の計算を分配法則という。
\(a \times (b+c)= a \times b + a \times c\)
\((a+b) \times c= a \times c + b \times c\)
中学ではこれを使って計算の工夫をしていきます。
気をつけてもらいたいのは左から右の計算だけでなく、右から左の計算もできることを意識してください。

「( )」を分解するだけじゃなくて、
「( )」を作りだすこともできるんだね!
2つの例を扱っていきます。
例 分配法則を利用して、次の計算をしなさい。
(1) \(\begin{align}
(\frac{5}{6} – \frac{1}{4}) \times 12
\end{align}\)
(2) \(\begin{align}
111 \times 13 – 11 \times 13
\end{align}\)

問題文に「分配法則を利用して」ってあるのはどうして?

これは分配法則がなくても解けるけど、分配法則を利用して簡単にできるように工夫してねっていう指示なんだ。
問題によっては「工夫して計算しなさい」って書いてあることもあるよ。
分配法則は工夫して計算できるかがポイントです。
うまく活用して解けるようになりましょう。
分配法則の活用
それぞれ解答を確認してみましょう。
(1) \(\begin{align}
(\frac{5}{6} – \frac{1}{4}) \times 12
\end{align}\)
(1)は本来「( )」内から計算をしますが、通分をしなくてはいけません。
それは面倒なので、分配法則をしてそれぞれ約分していきます。
解答
(1)
\(\begin{align}
(\frac{5}{6} – \frac{1}{4}) \times 12 &= \frac{5}{6} \times 12 – \frac{1}{4} \times 12 \\
&= \frac{5}{1} \times 2 – \frac{1}{1} \times 3 \\
&= 10-3 \\
&= 7
\end{align}\)
(2) \(\begin{align}
111 \times 13 – 11 \times 13
\end{align}\)
本来、(2)は\(\times\)からやりますが、計算が大変です。
ここでは「13」という共通で掛けている数があるので分配法則で1つにまとめます。
これがいわゆる「( )」を生み出す計算になっています。
解答
(2)
\(\begin{align}
111 \times 13 – 11 \times 13 &= (111-11) \times 13 \\
&= 100 \times 13 \\
&= 1300
\end{align}\)

これすごい簡単にできるね!
数字の共通点や分配法則などに気づくことができれば、計算速度があがること間違いなしです!
練習問題
計算の順序とかっこの扱い方、分配法則を使って素早い計算をすることを意識して組んでみましょう。
問 次の計算をしなさい
(1) \((-4)\times3-15\div(-5)\)
(2) \(4\times\{2-(1-16)\div5\}\)
(3) \(\{14\div(-7)\}^2+3\times(-2^2)\)
(4) \(29\times(-21)+21\times(-21)\)
(5) \(102\times(-16)\)
練習問題 解答
(1) \(-9\)
(2) \(20\)
(3) \(-8\)
(4) \(-1050\)
(5) \(-1632\)
練習問題 解答 途中式
各計算を以下に書いておきます。
途中式を含めて参考にしてください。
(1)
\(\begin{align}
(-4)\times3-15\div(-5) &= -12-(-3) ・・① \\
&= -12+3\\
&= -9
\end{align}\)
①の\(-15\div(-5)\)に関しては、\(-(-3)\)とせずに
\((-15)\div(-5)\)とみて、\(+3\)と考えても構いません。
(2)
\(\begin{align}
4\times\{2-(1-16)\div5\} &= 4\times\{2-(-15)\div5\} ・・① \\
&= 4\times\{2-(-3)\}\\
&= 4\times 5 \\
&= 20
\end{align}\)
①まず「( )」から計算します。
その後、{ }の中の計算をします。
\(\div\)があるのでそちらから計算しましょう。
(3)
\(\begin{align}
\{14\div(-7)\}^2+3\times(-2^2)&= (-2)^2+3\times(-4)\\
&= 4+(-12)\\
&= -8
\end{align}\)
累乗は指数の位置で計算が変わるので注意が必要です。
(4)
\(\begin{align}
29\times(-21)+21\times(-21) &= (29+21) \times (-21) \\
&= 50 \times (-21)\\
&= -1050
\end{align}\)
分配法則の活用です。
(5)
\(\begin{align}
102\times(-16) &= (100+2) \times (-16) \\
&= -1600 \times (-32)\\
&= -1632
\end{align}\)
こちらも分配法則の活用です。
最初の式では「( )」がありませんが、102を100と2に分解することで分配法則を活用できるようになるのです。
まとめ
順序と分配法則それぞれマスターしよう
いかがでしたか?
改めて今回の内容の復習です。
計算のルール
①乗法や除法は加法や減法より先に計算する。
②かっこ「( )」のある式はかっこの中を先に計算する。
③累乗がある式は累乗から計算する。
分配法則
次の計算を分配法則という。
\(a \times (b+c)= a \times b + a \times c\)
\((a+b) \times c= a \times c + b \times c\)
総集編ということもあり、複雑な計算が増えてきたと思います。
今回の内容をマスターできれば数のみの計算分野で困ることは基本ないでしょう。
他の分野では文字が入ってきますが、基本はここに揃っています。
忘れたら戻って演習。
その繰り返しを忘れず頑張っていきましょう!
それでは!
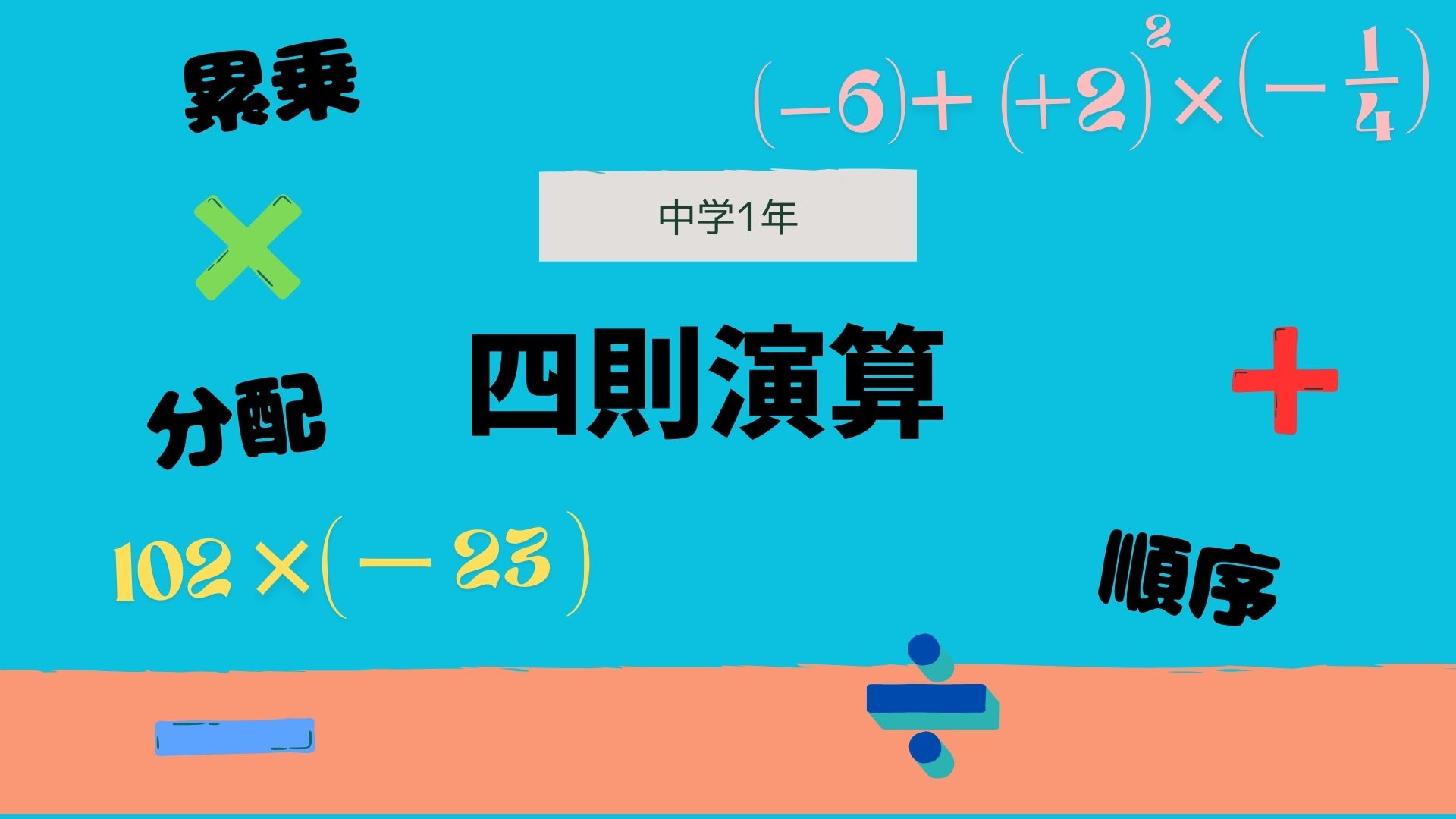


コメント